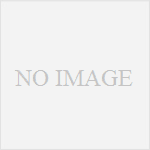昔、店をしていた頃、お客の常連とスタッフで、雑誌を発行していた。
『夏休みの友』というのだ。殆ど仲間内での雑誌だったが・・。
中心になっていたのは、それぞれの分野で広く活躍している面々だった。
その時、M子の<ジンタン中毒>の事を書いたことがある。
その原稿を先に読んだ人物で多方面において器用な男性が、
『少女M子』の話を見事に脚色をして笑わせてくれた。
許可を得てここに記載させて貰う。長いので2から3のつづくになる。
書いてくれた人物は、あだ名は<ジャンゴ><Django>
ジャンゴ・ラインハルトから来ている。店に来た時にかけていた音楽を、
彼が気に入った所から名付けたのだ。彼の本名を知らない人がいるくらいで、
当の本人もすっかり馴染んでいて、サインもDjangoと、していた。
ここではペンネーム朴念仁としている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「告白」
(14才・匿名希望)
採録・朴念仁
わたし、初めは嫌だったんです。だって、いつもウチのおじいちゃんなんかが
ヤニ臭い口を大きく開けて、ぼりぼりと噛み砕くのを毎日のように横目で見ていたんですから。
とてもあんなものが「キモチいい」ものだとはおもえなかったです。
だから、あの日、クラスメートのM子ちゃんから「キモチいいんだから、いっぺん試して
ごらんよ」って、すすめられたときも、正直言ってそんな気になれなくて・・・。
体育倉庫の裏の植え込みの所だったと思います。丁度掃除の時でみんな忙しく、
誰もわたしたちのことを見ていませんでした。最初は何度か断ってみたのだけれど
M子ちゃんはなかなか離してくれなくて。彼女って結構のめり込むところがあるもんだから、
いいえ、決して脅かされたとか、そういうのじゃなくって、だって、M子ちゃんたら
実際わたしの目の前で一掴み口の中に入れて見せてくれて、その時のM子ちゃんの、
うっとりとした表情を見ていると、わたしも何だか胸のところが、こう、締め付けられるみたいに、
なって・・・。気がついたら、わたしも五粒程口の中に含んでいたんです。
そして、「怖がらないでいいからね。そうっと、そう、やさしく噛んでごらん」って彼女が、
言うがままに口の中で噛み締めてみたら、つ~んとした刺激が舌の先から始まって、だんだんと
頭の芯までしみわたって行って・・。ごめんなさい、これ以上はとても恥ずかしくて・・・。
とにかく、気がついたら、わたし、植え込みのそばの芝生の上で気を失っていたみたいで、
M子ちゃんに揺り起こされて、それでもしばらくは身体中が火照っていて、
なかなか起き上がれなかったぐらいだったんです。
そう、この日からなんです。私がすっかり「J」の虜になってしまい、寝ても醒めても
あの銀色の粒のことばかり考えるようになってしまったのは。
それからというもの、朝や帰りの時には必ずといっていいほど、M子ちゃんと二人で「J」に、
耽るようになり、授業中でさえも、そっとセーラー服のポケットからあの円盤形の容器を取り出して
音がしないように何粒かを口の中に放り込む程深みにはまり込んで行ったのです。
こうして、気がつけば二人とも舌はぼろぼろになり、鼻はすでに何の臭いも嗅ぎ分ける事ができなくなり、
それでも、手持ちの「J」が切れると、指先が勝手に震えだすというありさまでした。
もちろん「J」のことは、M子ちゃんから固く口止めされていたので誰にも言いませんでした。
わたしたちにしてみれば、それが二人の間の秘密であることが余計に嬉しかったのだと思います。
なぜっていつも聡明で活発なM子ちゃんはクラスの人気者で、わたしに限らず、誰でも一度は、
M子ちゃんとSになりたがっていたんですから。わたしはM子ちゃんとの秘密を守ることに必死でした。
そして、あの「J」の快楽を求めて、少ないおこづかいをつぎ込み、それでも足りなければ、おじいちゃんの
「J」をこっそり抜き取ったり、挙句の果てには、水屋の引き出しのなかに入っているおかあさんのお財布に
手を出して、もう少しでみつかりそうになったりと、まるで不良少女のようになってしまっのです。
それでもわたしは幸せでした。二人ともお金がなくなり、たまたま拾った小銭でたった一袋の「J」を買って
分けあった時のこと、今でもはっきりと覚えています。もちろん、M子ちゃんには、多めにあげて、その分
わたしは袋に残ったにおいで我慢して・・・。ごめんなさい、泣かないつもりだったのに・・・。
だけど、本当に夢のような日々だったんですから。
つづく。