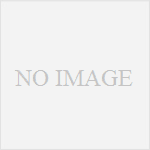<母に、抱かれているのは私>
父が帰って来た時だけ遅い時間でもうるさく云われる事もなく
少しは甘えられる時間が持たされていた。
でも父は余り娘たちの話は聞いていなかったように思う。
「うんうん」とだけ返事だけはしていたのだが。
自分が機嫌のいい時は土産を持って帰り、寝ている私たちを起こして
冗談を云い、受けて笑うと何度も同じ冗談を繰り返し楽しげあった。
そんな時の父は金回りが良く、私達もその事を把握していて、今だとばかりに、
学校でいる物や服、運動靴がもうぼろぼろである事など、姉と競って言い、
お金を貰う事が出来た。
こんな事がいつまでも続いてくれるようにと願いながら、息をひそめずに、
眠りにつける日であった。
父の事業が失敗し、母が出て行き、こんな生活を続けてもう4,5年なりかけていた。
戦前も戦争中も戦後も商才に長けていた父は、いくつもの会社を経営し、
父方の中では成功を収めた人と、親戚や母方の人間からも特別に扱われていた。
またその恩恵を受けて生活をしていた人間も多かったはずである。
気の良い父は 金があると後先を考えず人に振舞うところがあり、
よく騙されることもあったようだ。
そのためにいざという時の用意も用心深さもなく大らかにに生活していた。
商才があっても経営という点では 実際はどうであったかと思う。
祖母の家に転がり込むようになったこの事業の失敗は、相当に大きな物だったようであった。
住んでいた家や山や土地はもちろん、父が娘たちのために有名な人形師に
創らせた雛人形も、競に賭けられていた。
家の庭や道路にも、荷が運び出され、白い紙が張られ、訳の分からない人達が
口々に何かを言って白い紙を張っていく。
あまりにも幼い私は何も分からず、ただ不安感だけは強烈に覚えた。
後にその事が何かの折、胸をドキドキとさせることになる。
下の写真は兄の為に野球が出来るように、広場のような運動場があった。